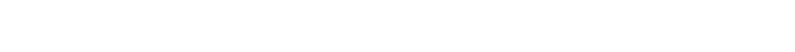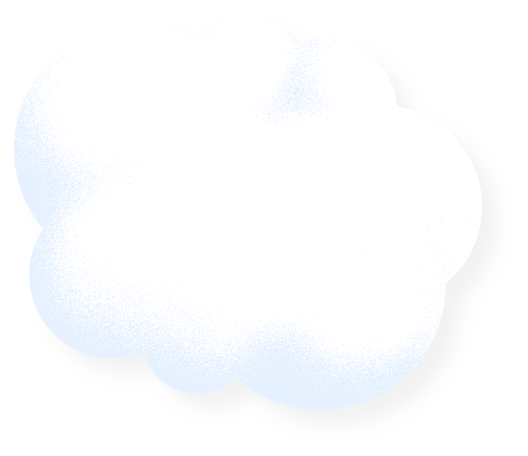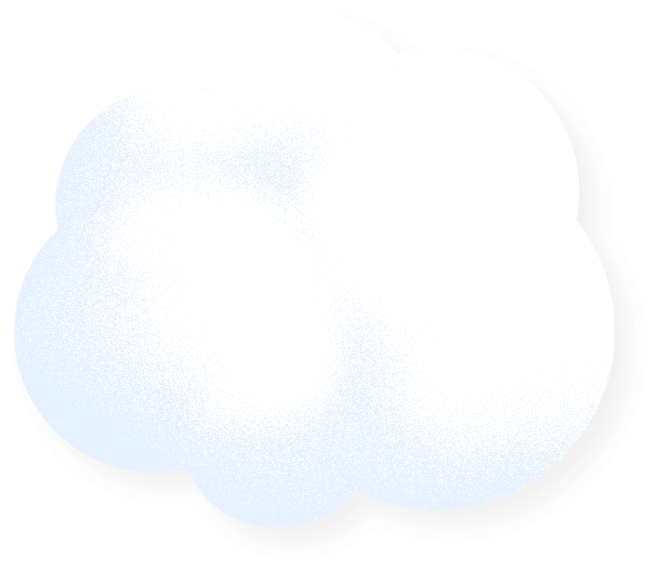心療内科・精神科
一般外来について
心療内科とは、ストレスや心の問題が原因で、体に症状が現れる場合に治療する科です。体の不調を心のケアを通じて改善します。
また精神科とは、不安やうつ、パニックなど心の病気や精神的な問題を専門に治療する科です。心の状態に焦点を当てた治療を行います。
竹内スリープメンタルクリニックでは、患者さまのご要望をお聞かせいただき、お一人お一人に合わせた医療提供を心がけています。
疾患の例

以下のような症状でお困りの方は、当クリニックへご来院ください。
- 最近、気分がずっと落ち込んでいる
- 意欲が出なくて食欲もわかない
- 電車など人ごみの中で急に不安に襲われる
- 身体がとてもだるくて生活がおっくう
- 動悸がするけれど病院で検査しても異常なし
- いつも誰かに見られているような感じがする
- 頭の中で誰かの話し声が聞こえる
- 次々にいやな考えや思いが浮かんでくる
- 誰かに狙われて襲われるような気がする
その他、職場や家庭におけるお悩みごと、出産前後のメンタルヘルスに関してもお気軽にご相談ください。
こころの病気について
うつ病は、慢性的に気分が憂鬱になったり、何事に対してもやる気が出ない状態が長期間続く病気です。
うつ病の早期発見は重要で、以下のような症状が2週間以上続く場合は心療内科・精神科に相談すべきです。
- 抑うつ気分、楽しめない
- 睡眠障害
- 食欲の変化
- 疲労感
- 無価値感や自責
- 集中力低下
- 死への関心
1. 薬物療法
コーヒー、紅茶、緑茶に含まれるカフェインやアルコール、過度な喫煙は、症状を悪化させることがあるため、これらを避けることが推奨されます。
2. 精神療法
認知行動療法(CBT)や対人関係療法(IPT)など、思考パターンや人間関係の改善を目指す治療法も有効です。
3. 休養
十分な休息は回復に不可欠です。無理をせず、家族や友人からの適度なサポートが重要です。家族は患者を過度に励ますのではなく、自然に見守る姿勢が求められます。
日本では約16人に1人がうつ病を経験しますが、適切な治療を受ければ回復が期待できます。焦らずに治療を続け、家族や医療従事者との信頼関係を築くことが大切です。
うつ病は誰でもかかり得る病気ですが、早期発見と治療によって回復が可能です。薬物療法、精神療法、休養を組み合わせ、周囲のサポートを受けながら治療に取り組むことが大切です。
双極症は、気分が極端に高揚する「躁状態」と、逆に気分が沈み意欲が低下する「うつ状態」が周期的に繰り返される精神疾患です。かつては「躁うつ病」とも呼ばれており、躁状態が目立たないためにうつ病と誤診されることが少なくありません。この病気は、症状の幅が広く、治療のためには正確な診断が不可欠です。特にうつ状態のみを見ていると、単なるうつ病との区別が難しく、治療法が異なるため注意が必要です。
双極症の症状は、うつ状態と躁状態で大きく異なります。うつ状態では、意欲の低下や強い疲労感、絶望感に加え、食欲や睡眠パターンの変化が見られることが多いです。一方、躁状態では、異常なほどの高揚感や自信過剰、エネルギーの過剰感が特徴的です。これにより、睡眠が極端に減少しても活動的になり、次々と新しいアイデアが浮かぶことがありますが、計画が破綻することもしばしばあります。
双極症には、軽い躁状態(軽躁状態)もあり、本人には異常と感じられないことが多く、周囲の人々が先に気づくことがよくあります。このため、診断が遅れ、うつ病として治療されるケースが見られるのです。特に注意が必要なのは、うつ病治療薬が躁状態を悪化させるリスクがあることです。
双極症の診断には、過去の気分変動や生活の様子、家族歴などを詳細に確認することが重要です。また、必要に応じて血液検査や画像診断も行い、他の疾患との区別をつけることがあります。診断が難しい場合でも、専門的な検査を通じて正確な診断が可能になります。
治療は主に薬物療法が中心となり、気分安定薬を用いて気分の浮き沈みをコントロールします。特に炭酸リチウムやバルプロ酸が代表的な薬で、これらは躁状態やうつ状態の再発を予防する効果もあります。また、重症の躁状態には、非定型抗精神病薬が併用されることがあります。
パニック症は、あるとき突然に理由なく不安に襲われ、「このまま死んでしまうのではないか」というほど激しい動悸や息苦しさ、発汗、めまいなどが現れる発作症状(パニック発作)を経験した後、その不安や恐怖が植えつけられてしまう疾患です。パニック発作は、10分~30分程度で収まることがほとんどですが、ちょっとした体調の変化にも敏感になり、「また発作が起きるのでは?」という予期不安が出現して不安感や緊張感が高まるようになります。
-
パニック発作が起こる
場所や状況に関係なく、突然パニック発作が起こります。
-
発作が、特定の場所や状況に紐づく
発作の経験が、発作が起こった場所や状況に紐づき、同じ場所や状況(似たような場所や状況)に直面したとき、緊張感が高まることでパニック発作を引き起こしやすくなります。
-
予期不安の出現
何度も発作症状を繰り返すと、パニック発作の経験が頭から払しょくできなくなり、「また発作が起きるのでは?」と不安感が強まります。不安の対象がパニック発作そのものから、それが起きた場所や状況に変わっていきます。これは特に、自分の意思だけでは逃れられない状況や場所で起きやすいです。
-
回避行動をするようになる
予期不安が強くなると、パニック発作に紐づけられた場所や状況に身を置くことに恐怖を感じて避けるようになります。徐々に場所や状況の範囲が広がっていき、この状態が進むと広場恐怖になります。
-
他者との接触を避ける
予期不安やパニック発作によって、人前で取り乱したり恥ずかしい思いをすることや、他者に迷惑をかけることを恐れるようになります。
- 交通機関(飛行機、新幹線、特急電車、バス、高速道路の走行、トンネル内の走行、橋)
- 知らない人に見られる場所(スーパーマーケット、満員の映画館、長い行列)
- 自分のタイミングでは離れられない場所(美容室・理髪店、重要な会議)
強迫性障害は、自分でもつまらないことだとわかっていても、そのことが頭から離れない、わかっていながら何度も同じ確認と行動をくりかえしてしまう性質の病気です。
たとえば、不潔に思えて過剰に手を洗う、戸締りなどを何度も確認せずにはいられないといったことがあります。
自分の意志に反して、何度も思い浮かんでしまう考えを強迫観念、そこから生まれる不安や苦痛を軽減しようとしてやめられなくなってしまう行動を強迫行為といいます。
汚れや細菌汚染の恐怖から過剰に手洗い、入浴、洗濯をくりかえす。ドアノブや手すりなど不潔だと感じるものを恐れて、触れない。
誰かに危害を加えたかもしれないという不安がこころを離れず、新聞やテレビに事件・事故として出ていないかを確認したり、周囲の人に何度も確認する。
戸締まり、ガス栓、電気器具のスイッチを過剰に確認する(何度も確認する、じっと見張る、指差し確認する、手でさわって確認するなど)。
自分の決めた手順でものごとを行なわないと、恐ろしいことが起きるという不安から、どんなときも同じ方法で仕事や家事をしなくてはならない。
不吉な数字・幸運な数字に、縁起をかつぐというレベルを超えてこだわる。
物の配置に一定のこだわりがあり、必ずそうなっていないと不安になる。
身体症状症は、身体に感じる痛みやしびれ、吐き気などの多様な身体的症状が長期間続く病気です。これらの症状は、検査結果や診察によって身体的な異常が見つからないにも関わらず、しばしば日常生活に支障をきたします。症状は体の異なる部位に現れ、しばしば変化します。患者は身体的な原因がないと受け入れるのが難しく、医療機関を転々とし、精神科受診に至るまでに時間がかかることがあります。
この病気は、以前は「身体表現性障害」と呼ばれていましたが、診断基準の見直しにより「身体症状症および関連症群」として新たに分類されるようになりました。
痛みや消化器症状などが続き、身体的な病気や薬物の影響では十分に説明できない状態。
重い病気にかかっている、またはかかりそうだという強い不安があり、実際には身体的な病気は存在しないか、ごく軽度である状態。
脱力や麻痺、感覚異常などが現れ、神経学的な障害が実際の病態生理学と矛盾する状態。
診断には、まず身体的な病気がないことを確認することが前提です。その後、精神的な原因が考えられる場合に診断が下されます。うつ病や不安症などの他の精神疾患が合併することもありますが、患者はその身体的症状に対して実際に苦痛を感じています。
治療法としては、まず身体的な問題がないことを理解することが重要です。薬物療法には、抗うつ薬や抗不安薬が有効であり、認知行動療法や精神療法も症状の軽減に役立ちます。症状を抱えながらもできるだけ日常生活を続けることが大切です。
適応障害は、生活環境の変化や出来事がストレス要因となり、様々なストレス反応が引き起こされることで、日常生活や社会生活が著しく障害される状態を指します。この障害は、環境に適応するための心理的・行動的な反応が正常な範囲を超えてしまい、生活に支障をきたすことが特徴です。
適応障害の症状は大きく分けて精神面と行動面に現れます。また、ストレスによる自律神経症状(例: 頭痛、めまい、動悸、腹痛など)や睡眠障害が伴うことも多いです。
- 憂うつ感
- 不安感
- 神経の過敏
- 涙もろさ
- イライラ
- 無断欠席や欠勤
- 物や人に対しての攻撃的な行動
- 過剰な飲酒や衝動的な買い物
ストレス要因は、個人的な問題から自然災害など、地域社会全体を巻き込むような出来事まで多岐にわたります。
ストレスに直面したとき、多くの人は一時的な感情や行動の変化を経験します。例えば、試験に合格した際に嬉しさで行動が積極的になることや、逆に失敗によって気分が沈んだり、不安定になることがあります。これらの反応が一時的であり、日常生活に大きな影響を及ぼさない限り、それは正常な反応と見なされます。
一方、適応障害では、ストレスに対する反応が強すぎるため、日常生活に支障をきたします。例えば、ストレス要因に対して抑うつや不安が過度に強まり、生活や社会活動に重大な障害が生じる場合、これは適応障害と診断されます。
適応障害は、原因となるストレス要因が明確であるため、原因が取り除かれれば症状は次第に改善します。しかし、職場や家庭内の問題など、持続的なストレス要因から逃れられない場合、症状が慢性化することがあります。
そのような状況では、ストレスに対する受け止め方を変える、または気分転換を図るといった対処法が治療の一環として重要になります。ストレスのある環境に適応するための「対処する力」を育てることも求められ、患者自身が積極的に治療に取り組むことが大切です。
適応障害の治療では、薬物療法と精神療法の両方が行われます。
薬物療法は、抑うつ、不安、不眠などの症状を軽減するために使用されますが、薬による一時的な症状緩和だけでは根本的な解決にはなりません。根本的な治療には、ストレス要因そのものの解決が必要です。
そのため、精神療法やカウンセリングが治療において非常に重要です。患者と医師が一緒にストレス要因の整理や解決策を考え、対処法を学んでいくことが、長期的な症状改善につながります。
社交不安障害(SAD)、または社会恐怖は、対人恐怖症や赤面恐怖症とも呼ばれていた障害で、人前で恥をかくことや恥ずかしい思いをすることを過剰に恐れる病気です。この恐怖感から、人前に出る状況を避け、生活や社会活動に大きな支障をきたすことがあります。
- 人前で話す際に頭が真っ白になる
- 緊張で顔が赤くなったり、震えが止まらない
- 食事や字を書く際、人に見られると過剰に緊張する
- 他人と接する場面で汗をかいたり、口臭が気になる
- 恥をかくのではないかという強い予期不安があり、その場面を避けてしまう
大きく以下のように2つに分けることができます。
・全般性のSAD:すべての社会的状況を避ける。
・非全般型のSAD:特定の状況のみを避ける。
SADは10代半ばに発症することが多く、25歳以上での発症は少ないです。強いストレスや過去の恥ずかしい経験がきっかけになることもあります。
SADの原因ははっきりしていませんが、生物学的な要因(脳の扁桃体や前頭葉の機能障害)、生育環境、過去の体験などが影響すると考えられています。扁桃体が過剰に反応し、恐怖や不安を強く感じることで発作的な症状が出ることがあります。
薬物療法
抗不安薬やSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)が用いられます。
認知行動療法
不安の原因となる考え方や行動パターンを見直し、不安に対処するための方法を学びます。
患者自身は強い悩みを抱えていることが多く、軽率な励ましは逆に苦しみを増すことがあります。心療内科や精神科の専門医に早期に相談し、正しい知識を持つことが大切です。
睡眠時随伴症は、睡眠中や覚醒時に起こる異常な行動や体験を特徴とする状態です。その中でも特に行動面で異常が顕著な3つの疾患について解説します。
レム睡眠行動障害は、主に中高年や高齢者に見られる障害で、夜間睡眠中に異常な行動が発生します。この障害では、夢の内容に基づいた行動が起こり、恐怖感や幻視、興奮状態に陥ることが多いです。通常、レム睡眠中は筋肉の緊張が消失して動けなくなりますが、この障害ではその緊張が持続するため、動作が可能になります。
この疾患は、レビー小体型認知症やパーキンソン病といった神経変性疾患との関連が指摘されており、本人や寝ている家族が怪我をすることもあります。治療には、異常行動を抑えるための薬剤が用いられ、特にクロナゼパムやメラトニン受容体作動薬が効果的です。
別名夢中遊行症[ソムナンビュリズム(somnambulism)]とも呼ばれるこの障害は、深いノンレム睡眠中に突然起き上がり、無意識のうちに歩き回る行動が特徴です。患者は目を開け、周囲の障害物を避けて歩きますが、意識はなく、会話もできません。翌朝、その行動に関する記憶が全く残っていないことが多いです。
この疾患は主に子どもに多く、発症しても成長とともに自然に改善されることが多いです。ただし、極めて危険な行動が伴う場合には、安全な睡眠環境を整えることが重要です。
夜驚症は、深い睡眠中に突然恐怖の叫び声をあげるなどの激しい反応を示す障害です。患者は、強い恐怖感に加え、動揺、心拍数の増加、呼吸困難、発汗などの自律神経系の異常反応を示すことがあります。
この症状は子どもに多く見られ、成長とともに自然に軽減することが一般的です。しかし、頻度が高く、症状が強い場合には、薬物療法が考慮されることもあります。
上記3つ以外にも、睡眠時随伴症には様々な種類があります。たとえば、悪夢障害や睡眠麻痺、さらには歯ぎしりや夜間下肢こむらがえりなどが含まれます。これらの症状も、睡眠中に体験する異常現象として分類され、生活の質に大きな影響を与えることがあります。
睡眠時随伴症は、年齢や個々の要因により異なる形で現れます。子どもに多い症状は成長とともに改善することが多いですが、高齢者に発症する場合は、神経変性疾患との関連が深く、早期の診断と適切な対処が重要です。
概日リズム睡眠障害は、体内時計(概日リズム)と外界の昼夜サイクルとのズレにより、望ましい睡眠時間帯に眠れず、日常生活に支障をきたす状態を指します。例えば、朝起きれない、遅刻が多くなる、または昼夜逆転の生活を余儀なくされることがよく見られます。
人間の体内時計の周期は約25時間といわれており、地球の一日24時間の周期とずれているため、外界のリズムに適切に合わせることが困難になる場合があります。このズレが原因で、睡眠と覚醒のリズムが乱れることがあります。
-
症状
明け方近くまで眠れず、昼過ぎまで目覚められない。無理に起床すると倦怠感や立ちくらみを伴うことが多い。
-
原因
体内時計が遅れており、自然な睡眠時間が遅くなってしまう。
-
影響
遅刻や欠勤の原因となり、全身の倦怠感やうつ症状が現れることがある。
-
症状
夕方から強い眠気を感じ、深夜や早朝に目が覚める。
-
原因
体内時計が進んでおり、睡眠と覚醒のリズムが早まる。
-
影響
高齢者や家族性のケースで見られることが多い。
-
症状
睡眠と覚醒の時刻が毎日1〜2時間ずつ遅れていく。
-
原因
体内時計が適切にリセットされないため、昼夜のリズムに合わせられない。
-
影響
長期の昼夜逆転生活が原因となることもある。
-
症状
睡眠と覚醒の時間帯が昼夜を問わず不規則になる。夜間の不眠や日中の強い眠気、昼寝の増加が見られる。
-
原因
体内時計のリセット機能が弱まっている状態や、社会的接触が少ない環境、長期間の三交替勤務等が影響する。
-
影響
睡眠のリズムが乱れ、生活リズムが不規則になる。
概日リズム睡眠障害は、生活習慣や環境の影響で悪化することがあります。治療には、以下の方法が効果的です。
朝の強い光を浴びることで体内時計を調整します。
睡眠のリズムを整えるための薬剤が使用されることがあります。
治療には、本人の治療意欲と生活習慣の改善が重要です。体内時計を整え、望ましい時間帯に睡眠をとることができるようになるためには、継続的な治療と努力が必要です。継続的な治療と努力により、朝起きれないや遅刻といった問題が解消され、日常生活の質が向上します。