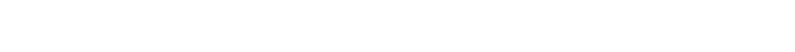睡眠外来
睡眠外来について
お悩みの方は当クリニックにご相談ください。
- 以前からよく眠れない、寝つきが悪い
- 寝ている間に何度も目が覚めてしまう
- しっかりと眠っているのに日中とても眠気を感じる
- 仕事中など気付かないうちに眠ってしまっている
- 睡眠が原因で学校に行けないことがある
- 眠れないことがだんだん怖くなっている
- 睡眠中、足を中心に不快な感覚が生じて寝つけない
- いやな夢をよく見ることがある など
睡眠障害とは睡眠に何らかの問題がある状態のことをいいます。睡眠が障害されると日中の活動に支障をきたし、心身の健康に影響します。また、日中にみられる睡眠障害の症状から事故につながることや、生活習慣病やうつ病のリスクも高くなることがあります。
当クリニックの睡眠外来は、このような睡眠障害でお悩みの方に対し、精神科領域の観点からも幅広く専門的に診断し、総合的に治療させていただくことを目的としています。

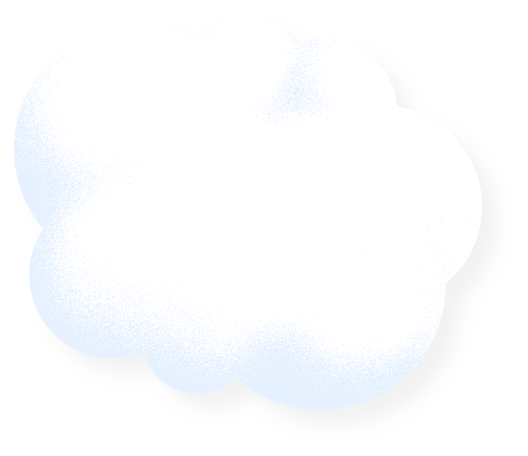
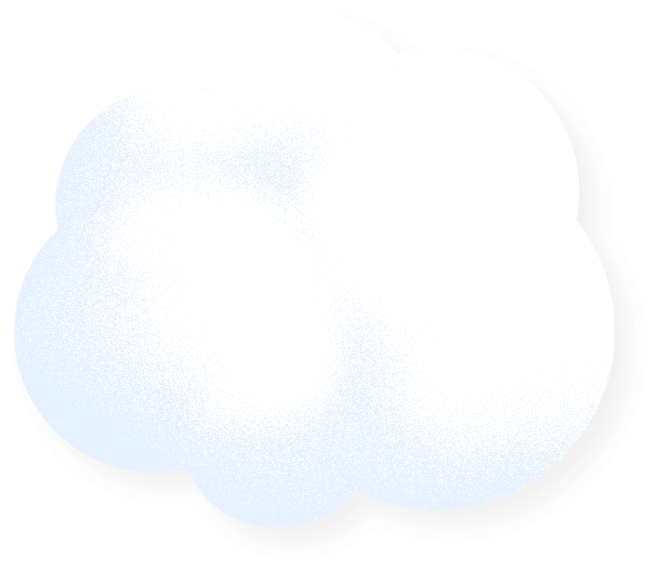
疾患の例

不眠症とは、眠れない、眠りが浅い、途中で目が覚めるなどの睡眠問題が長期間続き、日中に倦怠感や集中力の低下、食欲不振などの症状が現れる病気です。不眠の原因はストレス、身体的な病気、精神的な要因、薬の副作用など多岐にわたり、原因に応じた適切な治療が求められます。さらに、不眠が続くと「眠れないことへの恐怖」が生じ、過剰な緊張や睡眠へのこだわりがかえって不眠を悪化させる悪循環に陥ることがあります。
寝つきが悪く、なかなか眠れない
眠りが浅く、夜中に何度も目が覚めてしまう
早く目が覚めてしまい、再び眠ることができない
ある程度の時間眠っているのに、ぐっすり寝た感じがしない
睡眠時間には個人差があります。一般的には7時間程度が理想とされていますが、短い睡眠で十分な人もいれば、長時間眠らないと満足できない人もいます。年齢とともに中途覚醒や早朝覚醒が増えるのは自然なことであり、睡眠の質を気にするよりも、日中のパフォーマンスに注目すべきです。睡眠時間が短くても、日中に支障が出なければ不眠症とは診断されません。
不眠症の改善には、まず原因を特定し、それを取り除くことが重要です。以下は、日常生活でできる安眠のための工夫です。
就寝・起床時間を一定に保ち、体内時計を整えることが大切です。
無理に長時間寝床にいることは避け、眠くなったら寝るようにしましょう。
朝の太陽光を浴びることで、体内時計が調整され、夜に自然と眠気が訪れます。
午後に軽い運動を取り入れると、心地よい疲労が眠りを促します。
趣味やリラックスできる時間を設け、心身をリラックスさせることが大切です。
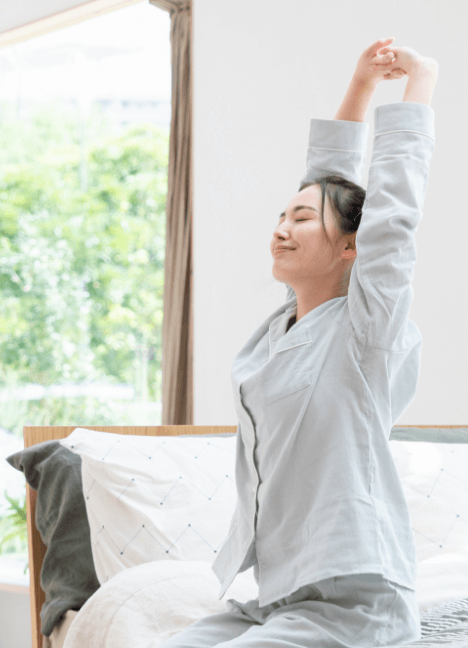
不眠が続くと、不眠そのものに対する恐怖や不安が増し、さらに不眠を悪化させることがあります。この悪循環を断ち切るためには、寝ようと無理をせず、眠くなるまでリラックスする時間を持つことが有効です。また、眠れないことで一人で悩むのではなく、専門医に相談することも重要です。
現代の睡眠薬は、安全で副作用も少なく、不安や緊張を和らげて自然に近い眠りを提供します。治療が進むと、薬の量を減らすことができ、最終的には止めることも可能です。

日中に強い眠気を感じたり、仕事中や会議中に寝てしまったりすることが多い場合は、過眠症の可能性があります。起きていなければならない時に眠気が強いと、日常生活や仕事に支障をきたすだけでなく、安全面でもリスクが高まります。
過眠症は、大きく分けて脳内の覚醒機能の異常によるもの(一次性)と、夜間の睡眠障害によるもの(二次性)があります。
一次性過眠症は、脳の覚醒機能に異常が生じることによって発症します。代表的なものには次のような疾患があります。
ナルコレプシーは、日中に突然強い眠気に襲われる疾患です。夜に十分な睡眠をとっていても、昼間に居眠りが頻繁に起こります。また、感情的な刺激によって筋肉が突然脱力することもあります。この状態は専門医による診断と治療が必要です。
特発性過眠症は、日中に強い眠気を感じる疾患で、ナルコレプシーよりも症状が軽いことが多いとされています。適切な診断と治療を受けることで、日中の眠気を管理することが可能です。
このまれな疾患では、強い眠気が2日から5週間続き、その後は無症状の期間が訪れることがあります。症状が年に1回以上繰り返されることがあります。早期の診断と治療が求められます。
二次性過眠症は、他の病気や状態が原因で日中の眠気が生じる状態です。主なものには以下があります
この疾患では、夜間に呼吸が停止することがあり、深い睡眠が得られないため、昼間に強い眠気が生じます。慢性的な酸欠状態が健康に悪影響を及ぼし、高血圧や心筋梗塞、糖尿病のリスクが高まります。早期の診断と治療が重要です。
睡眠時無呼吸症候群長期間の睡眠不足により、日中の強い眠気を感じる状態です。平日は短時間の睡眠をとり、休日に長時間眠ることが特徴です。規則正しい睡眠習慣を整えることで、症状の改善が期待できます。
ストレスや精神疾患が原因で、日中の眠気や集中力の低下が起こることがあります。ストレス管理や適切な精神的ケアが、過眠症の改善に役立つことがあります。
体内時計の乱れによって日中の眠気が生じることがあります。交代勤務や時差ぼけが原因で、睡眠と覚醒のリズムがずれることがあります。概日リズムを整えることで、症状を軽減することが可能です。
日中に強い眠気があり、居眠りなどで学業や仕事に支障がある場合は、睡眠障害専門の医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが重要です。専門的な評価と治療により、日常生活の質を向上させることができます。

むずむず脚症候群(RLS)は、脚の裏やふくらはぎ、太ももに不快感が生じ、じっとしていられなくなる病気です。症状は「むずむずする」「虫が這っている感じ」「ピクピクする」と表現され、患者は強い「脚を動かしたい」という欲求を抱きます。この症状は特に安静にしているときに現れ、夕方から夜間に強まります。欧米と比べて日本では発症率が低いとされていますが、それでも人口の2〜5%が潜在患者であり、200万人ほどが治療を必要としていると推定されています。女性に多く、特に40歳以上の中高年に多く見られます。
むずむず脚症候群は、脚の不快感や違和感が原因で、じっとしていられない状態になります。具体的には以下のような症状が報告されています。
- むずむず感
- 虫が這っている感覚
- ピクピクする、ほてる、ビリビリする
- 掻きむしりたくなる感覚
これらの症状は入眠障害や中途覚醒、熟眠障害を引き起こし、睡眠の質が低下します。その結果、日中の集中力や活動に支障をきたすため、生活の質(QOL)を著しく低下させます。
むずむず脚症候群の原因として、脳内の神経伝達物質であるドパミンの機能低下や鉄欠乏が関与しているとされています。特に鉄はドパミンの産生に必要な物質であり、鉄不足によりドパミンがうまく働かなくなることで、症状が引き起こされると考えられています。
むずむず脚症候群は以下の2つに分類されます。
原因が不明で遺伝的要因が関連している可能性がある。
他の病気や薬が原因で発症するケース。たとえば、慢性腎不全、鉄欠乏性貧血、妊娠、糖尿病、パーキンソン病、関節リウマチなどが挙げられます。
1.生活習慣の改善
コーヒー、紅茶、緑茶に含まれるカフェインやアルコール、過度な喫煙は、症状を悪化させることがあるため、これらを避けることが推奨されます。
鉄欠乏が原因のひとつと考えられているため、鉄分を多く含む食材(レバー、ホウレンソウ、あさり、いわし)を積極的に摂取することが大切です。
ウォーキングなどの軽い運動や就寝前のストレッチ、マッサージは、筋肉をほぐすために効果的です。
2.薬物療法
生活習慣の改善だけで効果が見られない場合、ドパミン作動薬や抗けいれん薬などの薬物療法が行われます。薬によって症状が改善されるため、治療を継続することで症状を緩和できます。
これらの症状があれば、むずむず脚症候群の可能性があります。
- 脚に不快感があり、じっとしていられない
- 安静時に症状が悪化し、脚を動かしたくなる
- 脚を動かすことで不快感が和らぐ
- 夕方や夜間に症状が強くなる